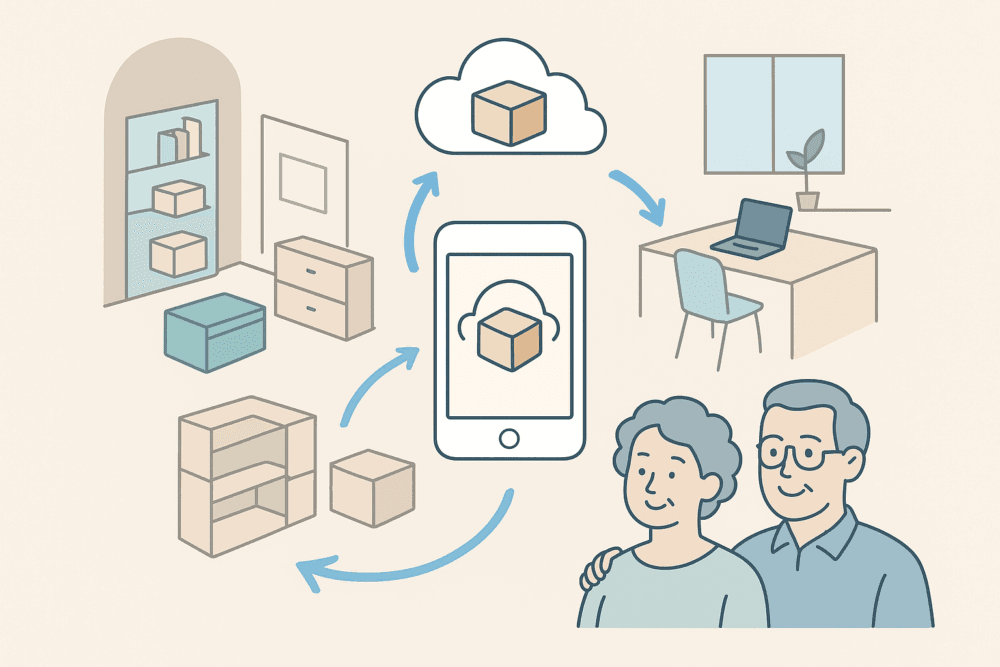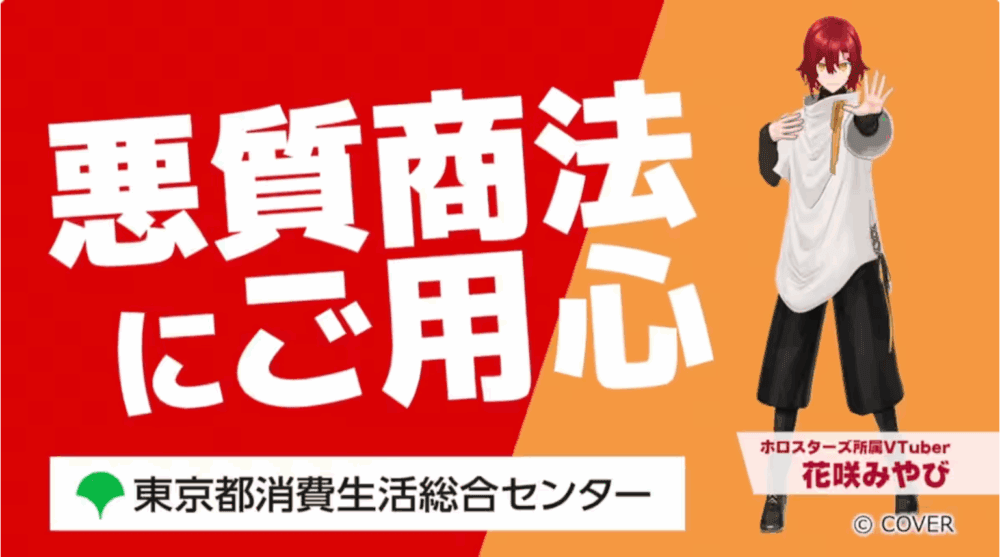100年後の未来に繋ぐ取り組みの意義。小林武史氏&北川フラム氏の豪華タッグによる「百年後芸術祭」、その中身とは?
この記事に該当する目標

千葉県誕生150周年記念事業の一環として、市原市、木更津市、君津市、袖ケ浦市、富津市の内房総5市で昨年9月にスタートした「百年後芸術祭-内房総アートフェス-」。このたび、3月23日(土)から5月26日(日)まで行われる、アート作品展示の出展アーティストが決定しました。国内外から気鋭の現代アート作家約70組が一堂に会する、豪華なアートフェスの中身をご紹介します。
100年後を見据えた、持続可能なプラットフォームとしての芸術祭


「百年後芸術祭 -内房総アートフェス-」は、豊かな海・里・食・観光資源を持つ千葉県を舞台とした、100年後を考える誰もが参加できる芸術祭です。後世に残していきたいアートや音楽、食について考えるきっかけになればとの願いを込めて、みんなで100年後の未来を創っていくための共創の場として誕生しました。
総合プロデューサーは、木更津市にあるクルックフィールズの代表を務める音楽プロデューサー小林武史氏。そして、アートの総合ディレクターは、地域に根ざした芸術祭を数多く手掛ける北川フラム氏が務めています。
本芸術祭で着目したいのは、アート・クリエイティブ・テクノロジーの力を融合し、100年後の新しい未来を創っていくための持続可能なプラットフォームとして活動している点です。「広域連携」「官民協同」による初の試みであり、そのコンセプトは“文化遺産や自然遺産をみんなで守り、後世に残そう”というSDGsのターゲットと合致しています。
3月23日(土)から5月26日(日)まで開催されるアート作品展示では、市原市、木更津市、君津市、袖ケ浦市、富津市の内房総5市で国内外から招聘(へい)された気鋭の現代アート作家による作品を鑑賞できます。市原市では、牛久商店街や市原湖畔美術館、旧里見小学校などの各拠点に約50作品が並びます。新設エリアとなる木更津、君津、袖ケ浦、富津の各市では、巡回しながらアート作品を鑑賞できるように、来場者への配慮も。それぞれ拠点となる地域を選定のうえ、作品が展示されます。
約70組の現代アーティストによる作品は見ごたえ満点
絵画、彫刻、映像、インスタレーションなど、さまざまな手法を用いたアート作品を手掛けるのは、総勢約70組の気鋭の現代アーティストたち。今回はその中から、梅田哲也氏、小谷元彦氏、SIDE CORE氏、さわひらき氏、千田泰広氏、名和晃平氏、リーロイ・ニュー氏、保良雄氏、ディン・Q・レ氏のプロフィールをピックアップします(日本人作家五十音順、敬称略)。
梅田哲也(うめだてつや) 日本
現地にあるモノや日常的な素材と、物理現象としての動力を活用したインスタレーションを制作する一方で、パフォーマンスでは、普段行き慣れない場所へ観客を招待するツアー作品や、劇場の機能にフォーカスした舞台作品、中心点を持たない合唱のプロジェクトなどを発表。先鋭的な音響のアーティストとしても知られる。近年の個展に「wait this is my favorite part / 待ってここ好きなとこなんだ」(ワタリウム美術館、2023-2024年)、「梅田哲也 イン 別府『O滞』」(2020-2021年)、「うたの起源」(福岡市美術館、2019-2020年)、公演には「9月0才」(高槻現代劇場、2022年)、「Composite:Variations / Circle」(Kunstenfestivaldesarts、2017年)、「INTERNSHIP」(国立アジア文化殿堂、2016年他)などがある。
小谷元彦(おだにもとひこ) 日本
1972年京都府生まれ。失われた知覚や変容を幻影として捉え、覚醒と催眠、魔術と救済、合理と非合理、人間と非人間など両義的な中間領域を探求する。また日本の近現代彫刻史の新たな脱構築に向けて、研究と実践を行う。ヴェネチア・ビエンナーレ日本館(2003)、リヨンビエンナーレ(2000)、イスタンブール・ビエンナーレ(2001)など多くの国際展に出品。立体作品のみならず多様なメディアを用い、綿密に構成された完成度の高い作品が内外で評価されている。近年の展示に「新しいエコロジーとアート」(東京藝術大学大学美術館、2022)、「リボーンアート・フェスティバル 2021-2022」(宮城県石巻市、2022)、「瀬戸内国際芸術祭 2022」(女木島)、「A Gateway to Possible Worlds」(ポンピドゥ・センター・メッス、2022)がある。2020年には「Public Device 彫刻の象徴性と恒久性」(東京藝術大学陳列館)のキュレーションを手がけた(共同キュレーター小田原のどか)。
SIDE CORE(サイドコア) 日本
2012年より活動をはじめる。公共空間におけるルールを紐解き、思考の転換、隙間への介入、表現やアクションの拡張を目的に、ストリートカルチャーを切り口として「都市空間における表現の拡張」をテーマに屋内・野外を問わず活動。「Yatsugatake Art Ecology」(山梨/2023)、「BAYSIDE STAND」(東京/2023)、「奥能登国際芸術祭 2023」(2023年/石川、珠洲市)、六本木クロッシング2022展:往来オーライ!(2022年/東京)、「水の波紋展2021」(ワタリウム美術館周辺、東京、 2021)、「Out of Blueprints by Serpentine Galleries」(NOWNESS、ロンドン、2020)。
さわひらき 日本/イギリス
石川県生まれ。ロンドン大学スレード校美術学部彫刻科修士課程修了。ロンドンおよび金沢を拠点に制作。映像・立体・平面作品などを組み合わせ、それらにより構成された空間/時間インスタレーションを展開し独自の世界観を表現している。自らの記憶と他者の記憶の領域を行き来する反復運動の中から特定のモチーフに光を当て、そこにある種の普遍性をはらむ儚さや懐かしさが立ち上がる作品群を展開している。主な展示に「Memoria paralela」(Museo Universidad de Navarra、パンプローナ、スペイン、2019)、「Latent Image Revealed」(神奈川芸術劇場、横浜、2017)、「Under the Box, Beyond the Bounds」(東京オペラシティアートギャラリー、東京、2014/Art Gallery of Greater Victoria、ブリティッシュコロンビア、カナダ)など。
千田泰広(ちだやすひろ) 日本
1977年神奈川県生まれ。長野県拠点。身近な素材と膨大な手作業で、体性感覚に働きかける空間を制作。欧州各国最大の芸術祭を中心に、約150の展示に参加。 Artdex「世界の9人の光のアーティスト」(2019)、米光学誌 OPTICA「光のアーティスト8人」(2022)に選出。リヨン(フランス、2021)、アムステルダム(オランダ、2017・2018)など、世界最大のライトフェスティバルへ参加のほか、大規模な回顧展が欧州を巡回。世界のライトアートを牽引。
名和晃平(なわこうへい) 日本
彫刻家/京都芸術大学教授/Sandwich Inc. 主宰。1975年生まれ。2003年京都市立芸術大学大学院美術研究科博士課程彫刻専攻修了。京都を拠点に活動を展開し、2009年、伏見に Sandwichを創設。独自の「セル(細胞・粒)」の概念のもと、彫刻の「表皮」に焦点を当て、ジャンルを横断した数々の作品シリーズを発表。彫刻の定義を柔軟に解釈し、鑑賞者に素材の物性がひらかれてくるような知覚体験を生み出してきた。2023年6月、フランス・セーヌ川に浮かぶセガン島にて高さ25mの新作《Ether (Equality)》を発表。
リーロイ・ニュー フィリピン
1986年フィリピン南部ミンダナオ島生まれ。マニラ在住。 フィリピン大学美術学部卒業。身に着けることができるウェアラブル・アートから大規模なインスタレーションまで、多彩な作品をつくる。また、「廃棄物」を素材として着目し作品制作を続け、フィリピンの芸術教育における欧米のスタイルから脱却し、植民地以前のフィリピン独自の芸術表現を探求している。 ハワイトリエンナーレ(2022)、ドバイエキスポ(2020)、シドニービエンナーレ(2022) などの国際展に出展。福岡アジア美術館のアーティストインレジデンス(2022)に参加。 2023年9月には、作品制作にあたり市原市内で海外にルーツを持つ大人や子どもとのワークショップを実施した。市原湖畔美術館では、市原市民から集めたペットボトルなどの廃棄物や竹を使い、高さ9メートルの吹き抜け空間を活かした巨大なインスタレーションを制作する。
保良雄(やすらたけし) 日本/フランス
フランスと日本を拠点に活動。2018年、東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。2020年、École nationale supérieure des beaux-arts 修了。テクノロジー、生物、無生物、人間を縦軸ではなく横軸で捉え、存在を存在として認めることを制作の目的としている。2018年ポートランドのアーティスト・イン・レジデンス「END OF SUMMER」に参加。主な展覧会に、「私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために」(森美術館、2023-2024)、「エコロジー:循環をめぐるダイアローグ つかの間の停泊者」(銀座メゾンエルメス フォーラム、2024)、「Reborn-Art Festival 2021-22」(宮城県石巻市、2022)、「Le 65e Salon de Montrouge」(パリ、2021)など
ディン・Q・レ ベトナム
1968年にベトナム、カンボジアとの国境付近のハーティエンで生まれる。ホーチミン在住。1978年、ボートピープルとしてベトナムを脱出、家族でアメリカへ移住。カリフォルニア大学サンタバーバラ校で学んだ後、ニューヨークのスクール・オブ・ヴィジュアルアーツで写真を学び、修士課程修了。2015年に森美術館で開催された個展「ディン・Q・レ展:明日への記憶」では、ベトナム戦争終結から40周年の節目に、歴史上で取り上げられてこなかった市民の声を拾った作品の数々を発表。2019年の瀬戸内国際芸術祭では、粟島でのリサーチと地元住民へのインタビューを元に《この家の貴女へ贈る花束》のインスタレーションを発表。ドクメンタ13(カッセル、ドイツ、2012)、シンガポール・ビエンナーレ(2008、2006)など、多数の国際展に参加。ケ・ブランリー美術館(2022)、ニューヨーク近代美術館(2010)などで個展。
百年後芸術祭のクリエイティブディレクターを務める大木秀晃氏は「100年後の未来はこうなるだろうな、自分だったらこうしたいな、そんな風に想像することもアート活動だと思うんです」と言います。作品を通じてアーティストたちが思い描く100年後の世界を体感しつつ、未来に思いを馳せてみませんか。
百年後芸術祭 -内房総アートフェス-のサイトはこちら
執筆/ライター・コラムニスト せきねみき