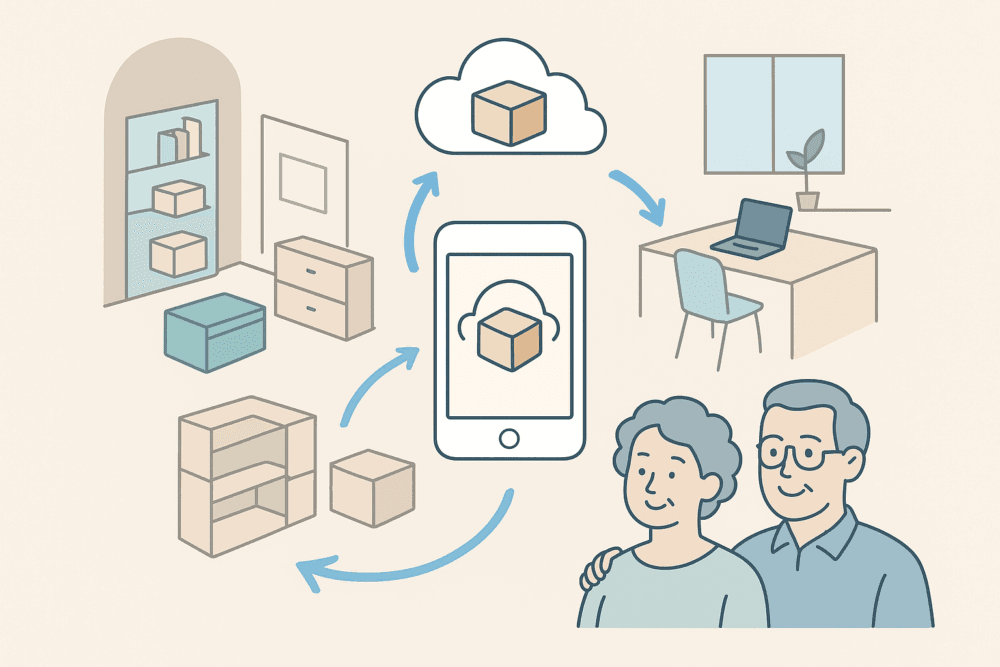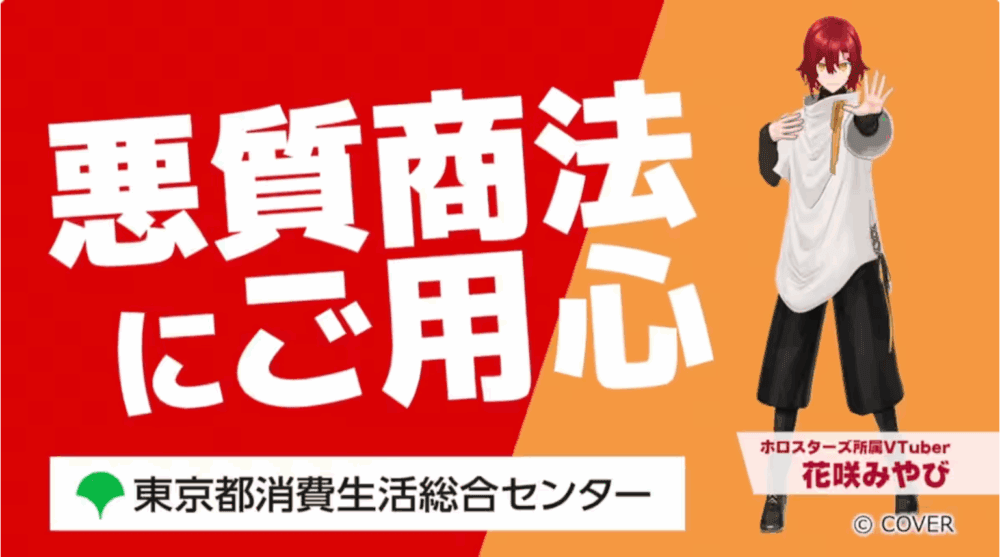冬バテ、引きずってない?待ちに待った春を元気に迎えるために意識したいこと
この記事に該当する目標


連日暖かくなり、待ちに待った春がとうとうやってきましたね!しかし、ちょうどそんな時に、冬の間に蓄積された疲れが表面化することもあるので注意が必要です。また、花冷えなどの寒の戻りや、暖かいと思って長時間外で過ごしていたら思ったより冷えてしまった、なんてことがあるのもこの時期。新しい年度をスムーズにスタートさせるためにも、体調管理はしっかりと行いましょう。
体調管理には、適度な運動や体温調整に加え、バランスの良い食事が欠かせません。今回は、管理栄養士の佐久間愛子先生に、自律神経の働きをサポートするとされる栄養素や、おすすめの温かい食事についてご紹介いただきました。
冬バテの大きな原因は自律神経の乱れ、コロナ流行後の生活環境の変化も心身の不良に影響?


夏バテほどよく聞かれる言葉ではありませんが、実は冬バテ、という不調があります。
冬の間、寒さに適応するため、体は血管を収縮させたり、筋肉を緊張させたりすることで体温を維持しようとします。これらの調整には自律神経が関与しており、交感神経が活発に働く傾向があります。しかし、交感神経の働きが長時間続くと、副交感神経とのバランスが崩れ、体の不調や疲労を感じやすくなることがあります。これが、密かに心配されている冬バテです。
冬バテには、発熱や風邪のような明確な症状がないため、気づかないうちにそのような状態になり、対処せずに過ごしてしまうケースも少なくありません。
冬の間に体調を崩し、それを引きずっていないか、まずは「冬バテ」の代表的な症状をみて当てはまるものがないかチェックしてみましょう。
□常に身体に冷えを感じる
□身体がだるい
□食欲不振または食欲過多
□気持ちがすっきりしない
□眠気がとれない
□夜なかなか寝付けない
□下痢・便秘をしやすい
□朝の寝覚めが悪い
□イライラしやすい
いかがでしょうか。当てはまる項目が多い方は、冬バテを起こし、それを引きずっている可能性があります。
冬バテ予防のポイントは自律神経を整えること
冬の寒暖差による疲労は、気温の変化や日照時間の減少により、自律神経のバランスが乱れることが一因と考えられています。心身の不調を防ぐためには、日々の生活の中で自律神経の調整を意識することが大切です。
自律神経のバランスを整えるためには、「冷え対策」「規則正しい生活」「バランスの取れた食事」 の3つを意識しましょう。例えば、体を温める食事を取り入れることや、適度な運動を習慣にすること、質の良い睡眠を確保することが、自律神経の安定につながります。冷えは、寒い時期だけの症状ではありません。寒くなくても体の一部が冷えていたり、冷房で冷えてしまったりすることはよくあるので、冬以外の季節にも意識しましょう。
「バランスの取れた食事」 で体の中から元気に


今回は、3つの中で特に意識したい「バランスの取れた食事」 について、詳しく教えていただきました。
今とるべき栄養素として佐久間先生が挙げたのは、「ビタミン」や「ナイアシン」、「マグネシウム」「鉄」です。
まず、免疫系の働きをサポートし、体内でのエネルギー代謝を助ける役割をするビタミンD。ビタミンDは、鮭やイワシ、卵、きのこ類などの食品に含まれています。また、紫外線を浴びることでビタミンDの合成をサポートする食品(干ししいたけや乾燥きくらげなど)もありますので、干物を選ぶ際は「天日干し」のものを選ぶことをおすすめします。
次に、三大栄養素(エネルギー産生栄養素)である「糖質」「脂質」「タンパク質」の代謝に必要なビタミンB群。三大栄養素は、私たちが生活するうえで欠かせないもので、人間の骨や筋肉、臓器、血管などを作ったり、脳や身体を動かすエネルギーになったりします。そんなビタミンB群は、種類毎に異なる働きをしているため、満遍なく摂取することが大切です。
そのなかでも特におすすめは、豚の赤身肉や、魚介類ではうなぎなどの動物性食品と、穀物や豆などの植物性食品に多く含まれる「ビタミン B1」、牛、豚、鶏肉、レバーや、マグロをはじめとした魚の赤身、ひまわりの種やピーナッツなどの種実類に多く含まれる「ビタミン B2」、動物性食品、植物性食品にかかわらず、多くの食材から摂取することができる「ビタミン B6」です。
ビタミンに続いて意識したいのは、幸せホルモンとも言われる「ナイアシン」。ナイアシンは、鶏肉やカツオ、たらこなどの魚類、キノコ類など多くの食材に含まれます。
そして、筋肉の収縮や血管の拡張に関与する重要な栄養素、マグネシウム。マグネシウムは免疫機能の正常な働きにも関与しており、エネルギー代謝をサポートするため、身体の健康維持にとって非常に重要な栄養素です。
主にごまやアーモンドなど種実類、豆類、大豆加工食品に多く含有されています。カルシウムを多く摂りすぎると、マグネシウムの排泄が増えてしまうので、マグネシウムとカルシウムは1:2の比率で摂り入れるのが望ましいバランスです。
最後に、全身の代謝を支える「鉄」。鉄は血液中のヘモグロビンを構成する重要な成分で、全身に酸素を供給する役割を担っています。酸素が適切に供給されないと、体の各部位が正常に機能しなくなり、最終的に自律神経のバランスにも影響を及ぼす可能性があります。そのため、鉄分が不足すると、疲労感や集中力の低下、さらには自律神経の乱れを引き起こす可能性があります。
鉄には動物性食品に含まれる「ヘム鉄」と、植物性食品に含まれる「非ヘム鉄」の2種類があります。
ヘム鉄はレバーや赤肉、赤身の魚など、動物性食品に多く含まれる鉄分です。体内に吸収されるのは約10~20%のため、毎日こまめに摂ることが大切です。
非ヘム鉄は野菜や豆乳、穀物、海藻、卵などに多く含まれます。非ヘム鉄の吸収率は2~5%程と、動物性食品に含まれるヘム鉄に比べて吸収されにくいですが、鉄不足の時は、吸収が高まるとされています。
体に嬉しい食習慣、朝の味噌汁と雑穀米
栄養素を満遍なく摂取する為にはごはんやパンなどの主食に加え、肉や魚などのおかず、野菜類の小鉢が1~2品あると良いですが、忙しい時に全てを揃えるのは難しいもの。そこで先生がおすすめしてくれたのが、体が温まる味噌汁です。味噌汁には内臓が温まり消化・吸収を良くするだけでなく、抗ストレス・リラックス作用が報告されているGABAも含まれています。さらに、今回紹介した栄養素が含まれている小松菜や豆腐、海藻類やきのこなどをふんだんにいれることで、忙しい朝でも少ない品数で必要な栄養素が摂取できます。
それに合わせて、主食にはビタミンB群補給のために玄米などの雑穀米がおすすめだそう。朝ご飯でお米を食べると胃腸が重くなるため難しい、という場合は、じゃがいもを味噌汁に加えると、鉄の吸収に役立つビタミンCも摂ることができます。
いかがでしたか。寒い時期の不調、冬バテをひきずってしまっているかも、という方は、ぜひ今回紹介した栄養素を意識してみてください。
栄養素についてもっと詳しく知りたいと思ったら、合わせて栄養素カレッジもチェックしてみてくださいね。
食べる健康、知る栄養- · 栄養素について、正しい知識を学ぼう
栄養素カレッジ
監修者
佐久間 愛子(さくま あいこ)先生


管理栄養士として介護・医療業界を渡り歩く。病院経験を経て予防医療の大切さに気付き、現在はICTでの特定保健指導に従事。また、糖尿病への理解を深めるため2021年に日本糖尿病療養指導士を取得。今までの経験を活かし、栄養・健康分野のライターとしても活動中。
執筆/フリーライター Yuki Katagiri